CANVAS LAB デキるシゴトを増やすメディア
マーケティング心理学を活用して顧客の心を動かす!今すぐ使える10個の行動心理学と活用事例を紹介
2022.03.11
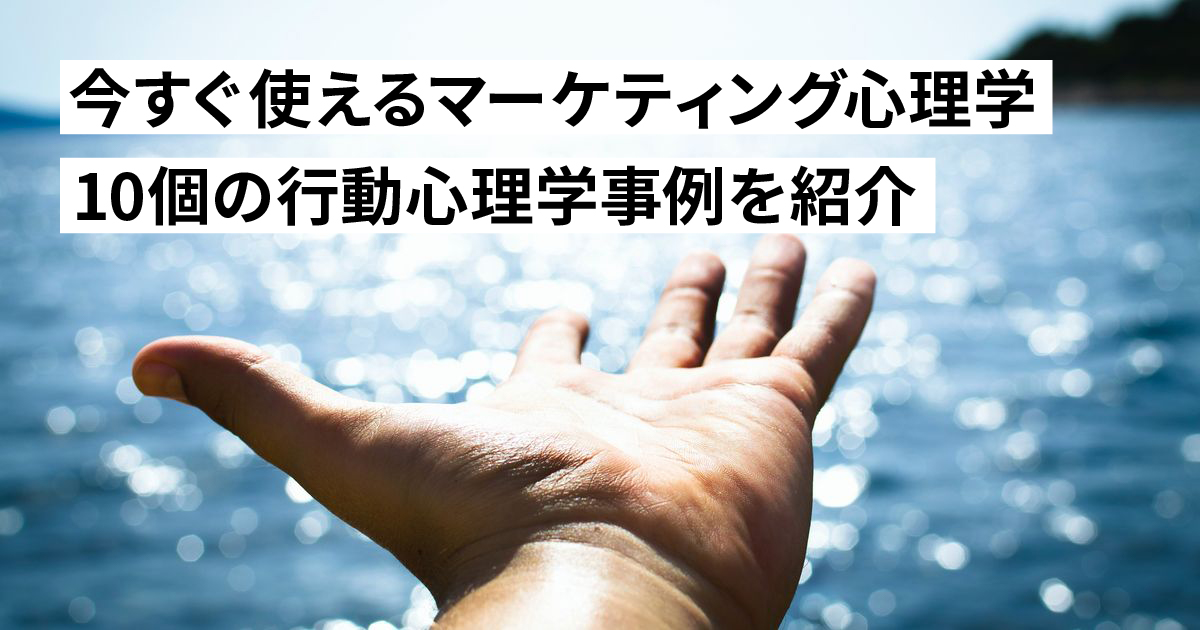
いつも使っているスマホ、いつも使っているパソコン。嗜好品から晩御飯の食材まで、私たちは日々、さまざまなものを購入し、利用しています。
これらの日常的な消費活動において使用したり利用しているモノ・コト・サービスは、いつから、なぜ使っているのでしょうか。
「必要だから」というにもありますが、「価値」を感じて買ったり、利用したりしているはずです。
同じように、企業が利益を上げるために自社の製品、サービスを利用してもらう際に、いかに顧客に価値を感じてもらうかの戦略を練るのがマーケティングです。
この時の「どのように伝えるか」はとても重要で、伝え方によって「価値」の受け取り方が大きくも小さくもなります。
では、どのように伝えれば「欲しい!」と思ってくれるのか。今回は、顧客に価値を感じてもらいやすくなるための、行動心理学に基づいた10個の今すぐ活用できるマーケティング手法について紹介します。
目次
バンドワゴン効果
1つ目はバンドワゴン効果です。
一生懸命呼び込みをしてるけど誰もお客さんが居ないお店より、すでに欲しい人がいっぱいで行列が並んでるお店の方が魅力的に映りますよね。
事実がどうであれ、人がいっぱい並んでいるという状況をみて「きっと人気だから人がたくさん並んでいるんだ」と考えてしまうのが人間です。
ある商品やサービスが多くの人に選ばれていることを証明することで、みんなが使っているものを使えば安心、みんなが利用しているモノを自分も利用したい、という心理効果を生みます。
バンドワゴン効果の活用事例
バンドワゴン効果についてはこちらの記事で詳しく紹介していますのでよろしければご参考にしてください。
>> バンドワゴン効果の意味と活用方法!マーケティングの行動心理学をビジネスに応用しよう
プロスペクト理論
プロスペクト理論は「損をしたく無い」という心理で、本来は合理的な判断をできるはずなのに、損を回避したいがために合理的でない行動をとってしまうという理論です。
例えば以下の質問をするとします。
確率的に言ったら、どう考えても「1.」の方が金額的にもお得だし得られる金額の期待値も大きいはずなのですが、多くの人は「2.」を選びます。
このように、損をしたく無いという感情によって合理的な判断が取れなくなるこをと説明しているのがプロスペクト理論となります。
プロスペクト理論の活用事例
返報性の法則
返報性の法則は、相手から親切にしてもらったり、何かを貰ったりした時に「お返しをしたい」と感じてしまう心理のことです。
「何かしてもらったことがある」という状態を作っておくことで、購入や契約への心理的なハードルが下がります。
さらに、「あなたに特別に」という演出があると、返報性の法則の効果はより強くなります。
返報性の法則の活用事例

ザイオンス効果
ザイオンス効果は、何度も繰り返して接触を持つことで好感度が上がっていく心理効果のことを言います。
例えば、営業マンがクライアント先にしょっちゅう顔を出したり挨拶にいくのも、油を売ってるわけではなく、このザイオンス効果を狙ってのことという場合もあります。
注意点として、嫌われてる場合やそもそもの魅力がない場合は、接触回数を増やしてもしつこいと思われてしまうだけです。
ただし、潜在的なニーズがある場合や、必要を喚起する意味では、接触頻度を高めて好感度を上げるザイオンス効果を狙うのは顧客と仲良くなるために有効な手段です。
ザイオンス効果の活用事例
ザイオンス効果についてはこちらの記事で詳しく紹介していますのでよろしければご参考にしてください。
>> 好感度を上げる「ザイオンス効果(単純接触効果)」とは?ビジネスやマーケティングでの活用方法を解説!
サンクコスト効果
サンクコスト効果はかけてしまった時間やお金、労力をもったいないと感じてしまうことです。日本語で言うと「埋没費用」となります。
例えばとあるスマホゲームに熱中して課金アイテムを入手した場合、「お金をかけて課金してしまったし…」と、ゲームに飽きてもずるずるとゲームを続けてしまう。
こういった状況もサンクコスト効果が影響していると言えます。
この心理を活用し、最初の参入障壁を低くしてまずは時間や、安いお金を使ってもらい、本来使ってもらいたい商品やサービスの利用につなげるというテクニックです。
サンクコスト効果の活用事例
バーナム効果
バーナム効果は、誰にでも当てはまるような抽象的なことを言われたときに、自分事にとらえてしまう心理効果のことを言います。
例えば占いのお店に来て「あなたは今、悩んでいますね?」と聞かれると「え!なんで知ってるの?」と感じてしまいますが、そもそも占いに来る時点で悩んでることがあるから行くわけです。
しかし、バーナム効果の影響で自分事にとらえて、その後の占い結果を信じやすくなる心理効果を生みます。
この心理を活用して、ターゲットとしてる対象だれにでもあてはまりそうな問いかけをしてから本題に入ることで、反応をよくするテクニックです。
バーナム効果の活用事例
カリギュラ効果
カリギュラ効果は禁止されると余計にやりたくなってしまう人の心理状態をいいます。
YouTubeやテレビCM、キャンペーンのキャッチコピーなどでも頻繁に活用されており、「〇〇の人は見てはいけません」「〇〇以外の人は閲覧禁止です」と言いつつも、実際には禁止せずに見れるようにしてあり、禁止することで気にしてもらい、見られる可能性を高めます。
これは、ダメと禁止したら見たくなる人間の心理状態を利用した手法となります。
カリギュラ効果の活用事例
カリギュラ効果についてはこちらの記事で詳しく紹介していますのでよろしければご参考にしてください。
>> カリギュラ効果のマーケティング活用術!絶対禁止の上手な使い方とは
スノッブ効果
スノッブ効果は、レアなものであればあるほど欲しくなるという心理状態のことです。
ある意味、先ほどのバンドワゴン効果とは逆の心理状態で、「他人と同じでは嫌だ。」「特別な自分は特別なモノを持っている」といった、希少性の高いモノ、状態に惹かれる心理です。
限定品であることや、希少性の高い機会に自分が選ばれていると思うことで、反応を高めることができます。
スノッブ効果の活用事例
ウィンザー効果
ウィンザー効果は、直接伝えられたことよりも、第三者より見聞した情報を信頼してしまう心理状態のことです。
例えば八百屋さんで
というと、カドが立ちますし、なんだか自慢っぽく感じてしまいますよね。
ところが、同じ八百屋さんでいつも買い物をしているおばさんが話かけてきて
と言われたら、なんだか信憑性がありますし、「ここのお野菜、買ってみようかな。」という気持ちになります。
この心理を活用して、第三者に自社の商品やサービスを評価してもらうことで反応を高めるテクニックです。
ウィンザー効果の活用事例
ハロー効果
ハロー効果は、「後光が指す」の後光効果とも呼ばれ、モノ、コト、人の印象が外部要因による干渉によって影響を受けることを言います。
例えば「5つ星ホテルのシェフ」といったら、それだけでもうおいしそうな料理が作れそうだとイメージします。
ネガティブなハロー効果を生む場合もあります。例えば、就職面談の時に、「大学受験3浪人」や「5年の未就労期間」といった事前情報があると、本人の能力やパーソナリティとは関係なく、「何か問題があるんじゃないか」といったネガティブハロー効果を生んでしまいます。
商品やサービスをリリースする時に、ひと手間かかりますがその道の権威の人に紹介してもらうことで、ハロー効果により権威をもつ人の後光効果を得られて反応を高められます。
ハロー効果の活用事例
ハロー効果についてはこちらの記事で詳しく紹介していますのでよろしければご参考にしてください。
>> ハロー効果とは?具体例やマーケティングでの活用事例を紹介!
マーケティングで行動心理学を上手に活用しよう!
今回は今すぐマーケティングで使える10個の行動心理学とその活用事例について紹介しました。
普段、何気なく買ったり、使ったりしているものでも、そこには利用してもらうための工夫が施されており、逆にそれらの工夫をこちらが活用することで自社のマーケティングに活用することが可能です。
顧客がいて、商品の魅力を言葉で伝える際に、ぜひ今回紹介したマーケティングテクニックを活用してみてください。
今回はこれで以上となります。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
