CANVAS LAB デキるシゴトを増やすメディア
製造業のDX推進、課題と解決ポイント
2021.09.24

製造業が抱えている課題の解決策として注目されているのがDX(デジタルトランスフォーメーション)です。「ものづくり大国」と言われてきた日本ですが、現在日本の製造業が危機に直面しており、さまざまな要因の課題解決のため製造業のDXに取り組むことが必要とされています。しかし、DXといっても、何を目指せばよいのか?何から着手すればよいか?と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。今回は製造業にとってのDXで解決すべき課題、DX推進ポイントについて解説します。
目次
DXとは

DX(デジタルトランスフォーメーション)は日本語で「デジタル変革」と訳しますが、デジタル技術を基盤にした時に起こる企業や産業への変化という「概念」と考えた方が理解しやすいと思います。
製造業にとってのDXとは
製造業には少子高齢化による人材不足、技術継承の停滞・IT活用不足のような課題があります。たとえば、人の感覚に頼って行なっている作業も、製造業には多く残っていますが、DXを導入し改革していくことで、より生産性の向上を期待されています。製造プロセスの属人化を防ぎ、代わりにデータ化・業務の自動化を目指すからです。
また、他社との競争という観点でもDX推進は必要です。現在は市場の変化が激しく、世界で競争力を維持するために、新製品や新サービスの生産をスピーディにし、世界に追随していけるよう体制を整えておかなくては、企業を存続できません。
製造業のDX化課題

データ活用が進まない
DXにおいてはあらゆる情報をデジタル化して収集、分析等に活用していくことが基礎となります。しかし、国内製造業では多くの企業が適切にデータ収集をできていないのが実情です。企業ごとの様々な事情でデータ活用が進んでいない中、製造業がこれからDXを進めていくためには、まずその必要性を理解しデータが集められる環境を構築すること、そしてそのデータをどのように活用すべきか考えなければなりません。
DXに必要な人材の不足
積極的にDXを推進したくても専門知識を持ったDX推進専門の人材がいなければ進め方がわからず成果が得られないでしょう。また最新のIT動向にも精通した人材を確保することは中小企業などでは特に難しいです。しかしその場合、コストはかかりますがDXを支援するサービスを活用するのがおすすめです。効率的にDXを進めることができ、内部の人員は本来の業務に集中することができます。
DXツールの選定が難しい
導入した企業はランニングコストの支出だけですぐにその機能を活用できます。データの収集から分析、その結果から現場での最適な意思決定や行動に繋げられるでしょう。データの収集から分析、その結果から現場での最適な意思決定や行動に繋げられるでしょう。しかしツールの選定を誤るとかえって業務効率を下げることにもなり、自社に合うツール見つかるまで無駄なコストがかかります。
製造業のDX推進メリット
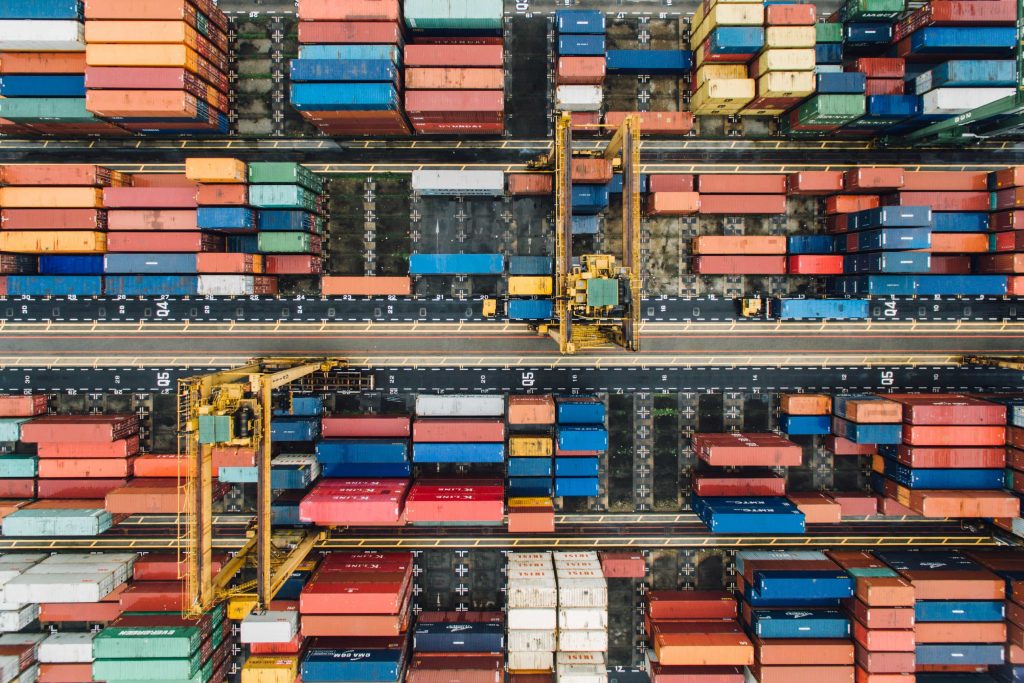
生産性が向上する
定型業務をデジタル化して効率化する。今まで手作業で集計していた不良発生の頻度計算を自動で集計するなど。製造業では、受注入力や生産実績の記録、在庫状況管理、出荷実績の記録などのさまざまな管理業務を、ITツールやIoT機器の取り入れることで無駄を省き、生産性の向上が見込めます。結果、生産コストや人件費の削減といったメリットを得られます。※IoT機器とは?パソコン・スマートフォンなどのIT機器以外で、インターネットにつながれたあらゆる物を指す(テレビやセンサー、監視カメラなど)
ニーズと開発の連携がとれる
市場のニーズと新製品開発を連携させる。データの収集・分析をし、市場の動向を把握しながら開発を進めることです。製造業では、部門別で情報共有が時差が生まれることが多いが新製品の開発に時間がかかってしまうと、先行者利益を失う可能性があります。DXによって社内の連携を強化し、同時進行で情報共有ができるようになれば、市場ニーズにあった新製品の開発から製造をより早く実現できるようになります。
顧客満足度の高い変革を行える
行動や考え方の変化に合わせたビジネスモデルの変革を継続的に行うこと。製造した製品を販売するだけでなく、顧客満足度やさらなる要求を確認する必要があります。またDXによって製造現場の生産性が向上すれば、新しくサービスやビジネスモデルを創出するために、より多くのリソースを割けるようになります。
製造業のDX推進ポイント

全社が一丸で取り組む
DXで解決すべき課題・どんな企業を目指すのかというイメージを最初に定め、ITツールを導入をしていくことが必要です。また、DXは個々の部門が独自に取り組んでいても実現することは難しく、経営者がリーダーシップを発揮し、全社が一致団結して取り組む必要があります。
製造業務の効率化や見える化
DXは、小規模な取り組みからスタートしてその都度検証を行いながら、次のステップへという流れを繰り返すことで、失敗のリスクを軽減することができます。初めに製造現場からツール、機器の導入によってアナログな業務を効率化、データを収集し現場の見える化と改善を進め、製造現場の生産性を向上させ現場の課題を解決することから始めていきましょう。
他部門と連携で全体の生産性向上
製造現場の生産性向上が進めた上で、他の部門との連携を強化し、企業全体としての生産性を向上させていことで、市場ニーズに合致した製品をより早く生み出せるようなります。
データの活用で新製品を創造
DXによってデータが収集・活用できれば、新製品やサービス、ビジネスモデルの創出がしやすくなります。また、既存の製品の付加価値を向上させることもできます。コスト削減、性能の向上やアフターサービスの充実といった付加価値を付け、顧客満足度を高めていくことができます。
まとめ

ここまで「製造業にとってのDX」の説明をしてきましたが、DXは概念であくまでも明確な定義があるものではありません。しかし、デジタル技術の進展により、世界中の企業が動き出しています。日本の製造業もこのデジタル前提の世界で1社1社がDXへ取り組むことで生産性や、顧客満足度を向上させ世界に負けない企業を目指していきましょう。
大切なことは、自社の状況を整理して、そこに潜む課題を洗い出すこと。そして課題解決のために現場が納得できる質を担保しながらデジタル化する必要があります。どのようにDXを始めたらよいか分からないという方も、本記事を参考に小規模な取り組みから少しずつ進めてください。
弊社では製造業向け展示会のオンライン化を推進しています。ぜひ製造業DXの一環としてオンライン展示会も取り入れてみてください。
